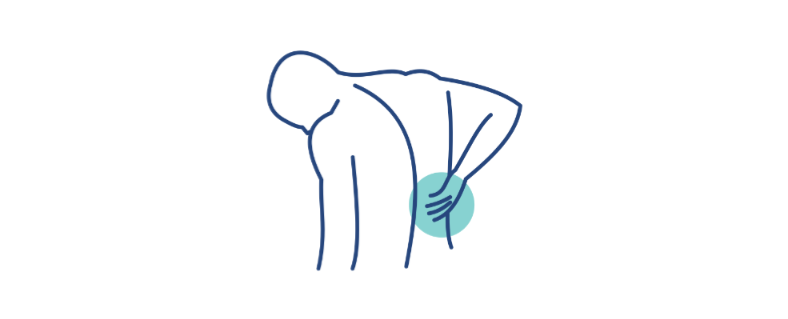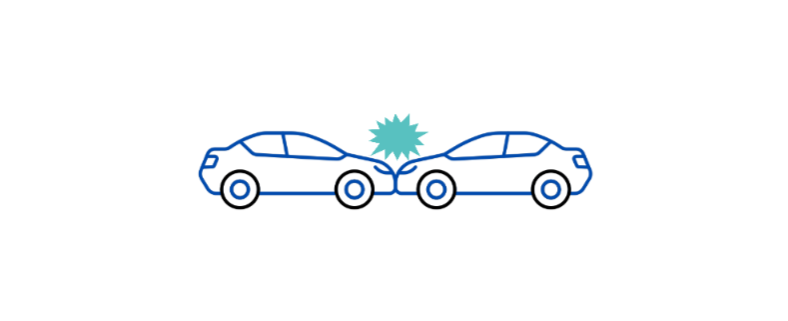「ずっと腰が痛い」「マッサージをしてもすぐ戻る」そんな腰の悩みはありませんか?
実は、腰痛の原因の多くは、骨や椎間板の異常ではなく、「筋肉(筋)」と「筋膜(きんまく)」にあるかもしれません。
レントゲンやMRIでは「異常なし」と言われたけど痛い…。そんな「原因不明の腰痛」の約3割は、この「筋・筋膜障害(きん・きんまくしょうがい)」によるものだと考えられています。
このブログでは、この「筋・筋膜性腰痛」がなぜ起こるのか、どこに原因があるのかを、皆さんが理解しやすいように詳しく解説していきます。
筋・筋膜性腰痛って、どんな腰痛?
1. 痛みの特徴:広範囲に及ぶ
筋・筋膜は、腰の周り全体を覆っているため、痛みが出る場所が腰だけにとどまらないのが大きな特徴です。
- 痛みの場所:腰だけでなく、お尻(殿部)、太もも(下肢)、背中(胸部)といった広い範囲に痛みを感じることがあります。
- 年齢層:若い人から高齢者まで、どの年代でも見られます。
2. 発症のメカニズム:負担の蓄積が原因
筋・筋膜性腰痛は、筋肉や筋膜に負担がかかり続けることで発生します。
- 同じ姿勢での作業:長時間のデスクワークなど。
- 前かがみの動作:家事や介護など。
- スポーツによる負荷:腰に負担のかかる動き。
このような負担が続くと…
- 微細な損傷や炎症が起こる。
- 血行が悪くなる。
- 筋肉が持続的に収縮することで筋内の圧力(内圧)が高まる。
これらによって、筋肉や筋膜が硬くなったり、動きが悪くなったりして痛みに繋がります。
また、事故や手術による腰周辺組織の損傷が原因となることもあります。
3. 画像検査ではわからない
重要な点として、筋・筋膜の異常はX線やMRIなどの画像にはほとんど映りません。そのため、「画像に異常がないのに痛い」という状況が生まれてしまうのです。
- 施術の落とし穴:「とりあえずマッサージ」の限界腰痛の患者様が来院された際、腰の筋肉をマッサージしたり温めたりすると、「楽になった」と言われることがほとんどです。これは、腰痛の原因がどこにあっても、その周りの筋肉や筋膜が緊張していることが多いからです。
しかし、もし椎間関節や他の部位に本当の原因(主となる病態)があるのに、筋肉や筋膜だけを施術しても、その場で楽になってもすぐに症状は戻ってしまいます。
私たち専門家は、「その腰痛の主犯は誰なのか?」を見極めることが非常に大切なのです。筋肉や筋膜への施術で一時的に良くなったとしても、「根本原因」を治療しないと、患者様はまた同じ症状で戻ってきてしまうことになります。
痛みの正体を探る!「筋膜と脂肪」のミステリー
「筋・筋膜性腰痛」の謎を解くには、筋肉の周りにある「筋膜」と、そのさらに上にある「脂肪層」の構造を理解することがカギになります。
1. 注目すべき「層」の構造
腰背部の皮膚の下は、まるでミルフィーユのように層になっています。
皮膚→脂肪層→筋膜→筋外膜→筋筋肉
この層と層の間が、体を動かすときにスムーズに「滑走(すべり)」することで、円滑な運動が可能になります。この滑走を担うのが、浅筋膜や深筋膜です。
- 痛みの司令塔:脂肪層の役割特に大切なのが、皮膚のすぐ下にある脂肪層と、そこにある浅筋膜・深筋膜です。
- 神経と血管:この浅筋膜と深筋膜には、痛みを感じる神経や血管が多く通っています。
- 滑走の重要性:この層の「すべり」が悪くなると、神経が引っ張られたり圧迫されたりして、痛みやしびれの原因になることが分かってきました。
2. 腰を支える強力な筋膜:胸腰筋膜
腰背部の奥には、下肢やお尻、背中の大きな筋肉を連結し、腰を支える「胸腰筋膜(きょうようきんまく)」という強靭な筋膜があります。この筋膜も、過度な負荷や滑走障害が起こると腰痛の一因となります。
3. 痛みを出す主要な筋肉:4つの主犯格
腰痛の原因となる筋肉は全身に及びますが、特に痛みを出す可能性が高いのは次の4つの筋肉です。
- 腸肋筋(ちょうろくきん):胸郭と骨盤を結び、体のねじれや横への傾きに関与。問題がある場合は、これらの動作に注目します。
- 最長筋(さいちょうきん):人体で最も長い筋で、脊椎近くを走り、体の前後の動き(前屈・後屈)に強く関与します。
- 多裂筋(たれつきん):腰椎の下部で特に厚くなり、脊椎の安定に重要。
- 腰方形筋(ようほうけいきん):体幹を横に曲げたり、骨盤を持ち上げたりする作用が中心です。
臨床的には、特に腸肋筋と多裂筋が痛みの原因となるケースが多いことがわかっています。
筋・筋膜性腰痛の痛みのメカニズム
筋・筋膜性腰痛は、なぜ広い範囲に痛みが出て、しかも「ぼんやりとした痛み」になりやすいのでしょうか?
1. 「ソーセージの例え」で理解する広範囲の痛み
筋膜は全身で多方面に連結し合っています。このつながりが、痛みの広がりに関係しています。
筋の過緊張:筋肉(筋実質)が硬くなると、内圧が上がり痛みます。
筋膜の硬さ:筋膜そのものが硬く(伸張性低下)なっても、やはり内圧が上がり痛みます。
これは、「中の肉が硬くなっても、包んでいる膜が硬くなっても、ソーセージは硬くなる」のと同じイメージです。
さらに、どこか一カ所の筋膜が硬くなると、その連結を介して周辺の筋膜も引っ張り合います。この「引っ張り合い」が、広範囲にわたる痛みや、少し離れた部位(関連痛)の痛みを生じさせると考えられます。
2. 体を動かしたときの痛み:「滑走障害」が主犯
筋・筋膜性腰痛は、前屈、後屈、ねじり、横への傾き、どの動作でも痛みが生じることがあります。
体を動かすとき、筋・筋膜は以下の動きをしています。
・体幹の屈曲(前屈):腰背部の筋肉と筋膜は伸張(伸ばされる)され、層と層の間が滑走(すべる)します。
・体幹の伸展(後屈):腰背部の筋肉は短縮(縮む)され、筋膜はたわみますが、この際も層と層の間が滑走します。
もし、この層間の「滑走」が障害される(滑走障害)とどうなるでしょうか?
・神経の伸張負荷:体の表面近くには皮神経という神経が張り巡らされていますが、神経はゴムのように伸びるわけではありません。体の動作に合わせて滑走(移動)することで、引っ張られないようにしています。
・痛み、しびれの原因:浅筋膜や深筋膜の滑走性が低下すると、この神経の滑走が阻害され、神経組織に伸張負荷(引っ張られる力)が加わります。神経は引っ張られることに弱いため、これが痛みやしびれを引き起こします。
特に、脂肪層の筋膜が痛みの原因の場合、患者様の訴えは「ざわざわする」「重だるい」「かったるい痛み」など、表面なのに深いような、曖昧な表現になることが特徴です。
3. 「縮む動作」でも痛むメカニズム
筋肉は伸びるときに痛むのは想像しやすいですが、縮むとき(例えば後屈)に痛むのは不思議に感じませんか?
これは、脊柱筋が多くの関節にまたがっていることに理由があります。内圧が高まった筋肉が、体幹の動きに応じて湾曲しながら短縮することになり、内圧がさらに高まることで痛みが生じると考えられます。これは、パンパンに張った水枕を曲げるイメージに似ています。
4. 痛みを4つのカテゴリーに分けて考える
筋・筋膜性腰痛を「ひとくくり」にせず、どこに問題があるかを明確にするため、私たちは痛みの組織を次の4つのカテゴリーに分けて評価しています。
1. 浅筋膜層:皮膚下の浅い脂肪層と筋膜。神経の滑走障害が原因。
2. 深筋膜層:深い脂肪層と筋膜。神経の滑走障害が原因。
3. 筋実質:筋肉そのもの。過緊張や内圧の上昇が原因。
4. 筋間の筋膜:筋肉と筋肉の間の筋膜。摩擦負荷や滑走障害が原因。
このカテゴリー化によって、評価と治療のターゲットを絞り、より明確なアプローチが可能になります。
あなたの腰痛の原因を特定する:評価プロセス
痛みを改善し、再発を防ぐためには、この評価プロセスが不可欠です。私たちは、「どこが痛いのか」(組織学的評価)→「何が悪化させているのか」(力学的評価)を順に解明していきます。
1. 組織学的評価(どこが痛いのか)
問診・視診と「疼痛除去テスト」を通じて、痛みを発している組織を特定します。
🔹 問診・視診で得られる情報
・痛みの広さ:広い範囲で手のひらで示すことが多い。
・痛みの質:「重だるい」「ざわざわする」など、曖昧な表現。
・きっかけ:はっきりしたきっかけがあるか、生活習慣や姿勢の関与が大きいか。
・動作との関連:どの姿勢・動作で痛むか、長時間の同姿勢で痛むか。
🔹 疼痛除去テスト(第3水準の評価)
これは、痛みが生じる動作を再現した状態で、原因組織に手技を加え、その場で痛みが消失・軽減するかを確認するテストです。
・原則:「表層から深層へ」順に評価します(浅筋膜層→深筋膜層→筋実質→筋間の筋膜)。
・浅筋膜層の操作:皮膚を介して、弱い圧力で「ページをめくるように」筋膜の滑走を促し、痛みが消えるかをテストします。痛みが軽減すれば、その層が痛みの原因だと特定できます。
このテストで、痛みの「主犯」が筋・筋膜であることを高い確率で同定できます。
2. 力学的評価(何が悪化させているのか)
痛みの原因組織が特定できたら、次にその組織に負荷をかけている「姿勢」や「動作」の癖を解明します。
🔹 立位・座位の姿勢評価
筋・筋膜性腰痛は、長時間の同じ姿勢による背筋群の過緊張で起こることが多いため、姿勢を重視します。
・長軸圧縮テスト:立位や座位で、重力方向へ軽く力を加えることで、筋肉の過剰な反応や痛みが再現されるかをチェックします。これにより、姿勢保持に伴う過剰な筋活動を見つけます。
・不良姿勢の修正:特に座位での「骨盤後傾、腰椎後弯、頭部前方変位」など、筋・筋膜に伸張負荷をかけ続ける姿勢を観察し、理想的な姿勢に修正して再度テストすることで、その不良姿勢が痛みの増悪因子だったことを証明します。
🔹 原因動作の評価
日常動作やスポーツ動作で最も痛む動作を観察し、不適切な体の使い方(例:腰を反りすぎた構え)が、特定の筋(例:多裂筋)にオーバーユース(使いすぎ)を引き起こしていないかを解明します。
根本改善へ!評価に基づく治療と予防
評価で特定された「痛みの組織」と「悪化させている負荷」に対して、最も適した治療と予防を行います。治療の目標は「筋の過緊張・滑走性低下」「モーターコントロール不良」「オーバーユース」の3つの悪化因子を改善することです。
1. 筋・筋膜のコンディション改善(ストレッチ・手技)
・徒手的な介入:硬い線維化や滑走障害はセルフケアが難しいため、まず専門家が手技で改善し、土台を整えます。
・段階的なストレッチ:背筋群は重力の影響を受けるため、臥位→座位→立位の順で重力位を上げながら、過緊張を改善するストレッチングを指導します。
・筋膜の伸張性改善:胸腰筋膜など全身の筋膜のつながりを意識し、反動をつけずゆっくりと伸張感を伴うストレッチを行います。
・腹筋群の活用:腹筋を収縮させることで背筋群を反射的に緩める(相反神経抑制)作用を利用し、過緊張を改善する運動も行います。
2. 体の動かし方のクセ(モーターコントロール不良)の修正
・機能評価を治療に:機能評価で使った腹筋運動や上下肢抵抗テストそのものが、正しい体の動かし方を学習させる治療になります。
・体感と定着:正しい動きで痛みや筋緊張が低下する「成功体験」を体感してもらい、それを自宅でのセルフエクササイズに繋げます。
3. オーバーユース(回復不良)への対処と予防
・生活習慣の改善:全身性のオーバーユースの場合、患者様と改善点を共有し、安静や生活習慣(睡眠、栄養)の改善に努めます。
・再発予防の鍵は「患者教育」:痛みが改善しても、再発を防ぐことが重要です。
・良好な筋状態の維持:長時間の同姿勢を避け、定期的に屈曲、伸展、側屈、回旋などの運動を行い、色々な動きに適応できる柔軟性を維持します。
・セルフ修正能力の習得:患者様自身が「痛みが出たときにどうすれば良いか」「どのエクササイズが自分に一番効果的か」を理解し、自分で悪い姿勢や動作を修正できる能力を身につけてもらうことが、最も重要かつ効果的な予防策となります。
あなたの長引く腰痛は、適切な評価と治療、そして生活習慣の改善によって必ず改善できます。痛みで諦めてしまう前に、まずはご自身の「筋・筋膜」が発するサインに耳を傾けてみましょう。
次の一歩:
あなたの腰痛が「筋・筋膜障害」によるものなのか、専門的な「疼痛除去テスト」で原因を特定し、あなた専用の「姿勢・動作の改善指導」を受けてみませんか?
ご相談、ご予約はいつでも承っております。
京都市西京区の上桂なごみ整骨院